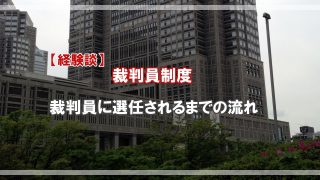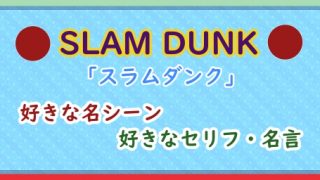良く聞きますよね。難しいことを誰にでもわかるように説明できるのが頭の良い人って。
でもこれ全く間違いだと思うんです。少なくても私の周りにはこんな人は1人もいません。今回はそんな話を書いてみます。
★目次(もくじ)
頭の良い人は、理解できない人に説明などしない
これがすべてだと思うのですが、頭の良い人は自分がストレスなく吸収できるようなレベルの話を聞いて、自分はしっかり理解してしまいます。
でも基礎知識が足りなかったり、専用知識や教養などの部分が不足して同じ説明でも理解できなかった人には、そのあたりの知識や説明を踏まえてフォロー必要になりますが、、、
そもそも頭の良い人は自分が理解できていることについては、他人も大差ないと気に留めることもなく、わざわざ不足分の知識などを踏まえて細かく説明してくれるようなことはほとんどありません。
自分がわかりきっていることを他人に説明する必要も感じることもないし(当然わかっていると思っているし)、そんな余計なことをしてもという思いもあるのだというところで、
結局、単に頭の良い人は、理解できない人を気にして、わかりやすく説明をするようなことはほとんどありません。
ですので、頭の良い人は誰にでもわかるように説明できる というような言葉が巷であふれているのは、『説明してほしい』という逆側からの願望から生まれてきた言葉なんだと感じますね。
教育を理解している人は、どんなに理解できない人にも説明できる
前文までだけだと、じゃどうすればというような気持になってしまいますが、言葉を正しくすれば問題なくなります。
そう、
『教育を理解している人は、どんな理解である人にも説明できる』
というのが正しいです。単に頭が良いだけじゃ人は導けないってことですね。
相手のレベル、理解度、持っている知識等をしっかり把握し、理解すべきことへのゴールまで必要なものを与えつつ、到達させる。これが教育の1つです。
そして、次のステップではなぜそのような考えに至るのかという正しい思考力への導きや、正しい判断を選択できるような地力を備えさせるように育む。
そう、教育とは教え育むと書きますよね。人間は生まれたときから自分の頭で考え、判断し行動することを永遠に続けていくわけで、これを正しく導いてあげるのが教育です。
それは、子供の教育も、新人教育も基本は同じで、自分で正しい判断、思考ができよう導くこと。
その1つとして、
『教育を理解している人は、どんな理解である人にも説明できる』
という1場面が切り取られた言葉というのが今回は正解なんだと思いますね。
教育は我慢と忍耐の繰り返しです。愛情をもって接していけば必ず伝わると思います。